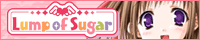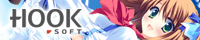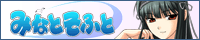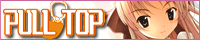「……ん?」
突如、謎の声と共に鍵士たちを包み込んだ光。その中で、鍵士は恐る恐る目を開いた。
「こ、これは……、剣なのか?」
驚くことに鍵士の右手には光り輝く“剣”がしっかりと握られている。その刀身は神々しい光を放ち、柄の部分は黄金の装飾がされている。この世の物とは思えないほど、美しく感じた。
その時、さっきの光で目を覆いながら蹲っていたリリュークが立ち上がった。
「まさか……! あれはまさしく、選ばれし勇者の証にして伝説の聖剣、いや、最強とも称されし名剣、『エクスカリバー』!何故そのような代物がやつの手から……!?」
エクスカリバー、それがこの剣の名……。もし、今のリリュークの説明通り、これが伝説の聖剣ならリリュークも倒すことが可能なのだろうか?
――よし、ここはこの剣に懸けてみるしかない!――
鍵士はそう考えると、手に持つエクスカリバーを身構えた。全く剣の持ち方すら知らない俺だったが、見様見真似、RPGゲームでよく見る剣士が剣を構えるような感じででエクスカリバーを構えた。
「はっ!? なんだその構え方は? ふ、どうやら剣の正しい構え方すら知らぬようだな。いくら貴様の持つ剣が伝説のエクスカリバーだとしても、それはやはり宝の持ち腐れということか!」
リリュークは空まで響き渡るような声で高笑いをした。
「それでは貴様を殺し、そのエクスカリバーを我が宝にするとしよう! そうだ、それがいい! 剣の持ち方すら知らぬ主より、我が物になりし方が喜ぶだろうしな!」
確かにリリュークの言うとおり、やはり見様見真似ではどんなにこの剣が伝説のエクスカリバーであっても、俺にとっては無意味なただの金属の棒にしかならない……。やはりこの状況でやつを、リリュークを倒す事は不可能なのか……!
「――それは違います」
――さっきの声!?――
「――その剣は勇者の証。だからあなただからこそ真の持ち主」
――ま、待てよ! でも……、俺は剣とかそういうものの使い方なんか知らないし。それでどうやってあんなやつに勝つことが……――
「――私を信じて下さい。あなたが純粋な気持ち、その勇者に相応しい心の持ち主なら、きっと、きっとやれます……」
――え、おい!――
誰だか分からない不思議な声と、俺は心で会話している。これが所謂、『テレパシー』と呼ばれるものなのか? いや、そんな場合じゃなくて、俺ならやれるって、でもどうすりゃ……。
その時、ふと目に凜の姿が映った。凜は目を瞑ったまま、微動出せず、静かに眠っている……。
――やるしかないんだ! 今は、凜のためにも、俺がやつを殺ることだけが、せめて凜のためにもしてあげられる事だ!――
鍵士はエクスカリバーを構え、そしてリリュークの方へと駆けだした。
「うおおおおぉぉ!」
それはまさに考え無しの“突進”攻撃、そのものだった。
「は! 戦い方を知らぬ貴様に何が出来る!」
――キュイーーーーン!
その時、鍵士の手に電撃のようなものが走った。一気に体中の血が騒ぎ出すような、全神経が剣を持つ手へと注ぎ込まれる感覚。今なら自分でも戦える気がする!
「そりゃっっあ!」
エクスカリバーが夕焼けの空を掻き切るように、舞った。
「くっ!」
まるで剣舞のように、エクスカリバーは鮮やかに、そして速く、リリュークへと正確な斬撃を繰り出している。自分でも疑ってしまうほど、エクスカリバーを使いこなしている。意識的ではなく、もはや本能による攻撃だった。『リリュークを殺す』。それだけが全ての衝動の要因である以外、残りの感情など何も無い。これが“人を殺す”ということなのだろうか……。
「調子に乗るなっ!」
リリュークはナイフでの防御から一転、隙を見て鍵士の攻撃を素早く回避し、ナイフを突き立てて攻めへと転じた。
「負けるか!」
鍵士へと止め処なく、突きの連続攻撃が襲いかかる。だが、鍵士はそれをかわす事無く、エクスカリバーで全ての攻撃を受け止める。もはや鍵士の目には、リリュークの動作一つ一つが正確に映っていた。残像さえもが。
「いくぞ!」
鍵士はリリュークのナイフを薙ぎ払うと、一瞬怯んだリリュークへとエクスカリバーを振り下ろした。
「チッ!」
惜しくもリリュークは瞬時に後ろへと飛び跳ねるとその攻撃をかわし、そのまま鍵士と数メートル、距離をおいた。
「まさかこれほどとは……。やはりこれが選ばれし者の力なのか。ならば俺も本気を出さねばな!」
「ハァ、ハァ……、そんな、本気だと……!」
「その通り。今までのは俺がこの人間界で暗殺家業の為に編み出した独自の暗殺術。よって概念の主としての力は使用していない、というわけだ」
「それじゃあ、今までのはあくまでも……、本気ではなかったってことなのかよ!」
「フハハハハ! その通りだ、久遠鍵士! それでは見せてやろう、概念の主と呼ばれし真の我が力を!」
すると、コンクリートの地面に映るリリュークの黒い影が一瞬、陽炎のように揺れた。最初は気のせいだと思ったが、影は揺れながら徐々にその大きさを増し、もはや影の大きさは屋上全域を覆い尽くさんばかりだった。
「これは一体……!?」
「さあ、今こそ我が真の力を見るがいい! 出でよ、東国最強の大蛇、『ヤマタノオロチ』!」
巨大な影が波打つように動き出したと思うと、急にその姿を変えていき、平面だった影は立体化する。その姿は、俺も聞き覚えがある、日本神話上、最凶最悪と謳われし八つの頭を持つ蛇の王、八岐大蛇そのものだった。すでに日は沈みかけているためか、ヤマタノオロチと呼ばれる怪物の八つの頭の目全てが爛々と朱く光っている。口には長く鋭い牙、また影と思われし身体の皮膚は黒く重厚な鱗、つまり鉄壁の鎧まである。
「これが……、真の力……なのか」
「そう、これこそが俺の真の力であり、昔、とある日本の西国の地にて封印されていたところを見つけ解放し、今でも使役しているヤマタノオロチだ。その力はかつて俺が使役していた西欧の蛇の王、バジリスクにも匹敵する。まさに最強の蛇……!」
リリュークの下半身はヤマタノオロチの頭の一つと同化しており、上半身だけが姿を現している。
「嘘だろ……。こんな化け物、どうやって倒せっていうんだよ……」
「フフ。そうだ、自らの絶望感に飲み込まれるがよい。そうして、そのままヤマタノオロチに飲まれ、俺の体内に取り込まれるがいい!」
ヤマタノオロチはその八つの首を鍵士の方へと伸ばした。見た目が重そうなのにもかかわらず、そのスピード、何より異なった八方向からの攻撃が鍵士へと襲いかかった。