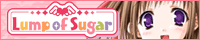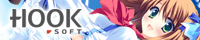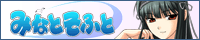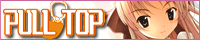――寝坊してしまった。
目覚まし時計の針は、既に7時を指している。起床予定時刻は6時。つまり1時間も寝坊してしまったのだ。
「新学期早々寝坊するとは、俺もなかなかやるな……」
と感心している場合じゃない! 確かにいつもの俺ならこのまま二度寝へと突入、するのが普通だ。
第一、そこまで学校に早く行ったって、三文の得にもならん。むしろ損だ。しかし、それならば何故目覚ましをかける必要があったのか、という疑念が残る。
実はこれには深くない理由がある。
なんたって今日は高校2年生の最初の登校日、つまり新学期の幕開けなのである。
幕開けっていうほど大袈裟な事じゃないと思う人もいるだろう。だがそうもいかないのが事実なのである。
はっきり言えば今日は『クラス替え』と呼ばれる儀式があるのだ! 「だから何?」と思った諸君、君は本を読まないのかね!?
学園恋愛ものの、ライトノベルを本屋さんで手に取ってみるがよい。全てという訳では無いが、ほとんどの作品は大概、
クラス替えをした時、好きな女の子と一緒のクラスになって、それから二人の仲は急接近ーーー! みたいな展開が定石なのだ。
これで分かっただろう。いかに今日という日が重要なのかということを。その影響力たるや、俺の人生を左右する程のものだろう。
思い返せば、高校に入学してから丸一年、『恋愛』とかいうものを味わうことは一度もなかった……。
もし、俺の高校が男子校だったらこんな状態なのも普通として受け入れられるが、現実に周りには少なからず女子は十分にいる。
なのに何故だろうか、俺に恋愛話は全く来ない。
別に人付き合いが苦手という訳でも無く、友人もそれなりにいる。学校生活もそりゃまあ、完璧とは言えなくても順調に送っている。
理由は大体見当が付いている。それは、俺自身、『恋愛』に対してかなり鈍感だからだ。初めて気付いたのは、女友達から
「鍵士って結構、鈍感だよね~。あんまり、女子が何考えているか分かってないでしょ。それ、ちょっとマズイかもよ。
下手すると彼女出来ないかもよ」
いきなりそんな事を言われてもどうしようも無い。
「それじゃあどうすりゃいいんだよ」としか言いようが無い。
つまり俺は鈍感なのだ、と行き着くまで果たしてどのくらい時間をかけたのか……。
だからこそ今年こそは、何としてもその鈍感さを克服する! 具体的に言えば、絵莉菜に告白するというのが目標なのだ。
絵莉菜っていうのは本名「如月 絵莉菜」、かれこれ幼馴染みという関係を10年ほど継続している女子である。
絵莉菜とは親ぐるみで昔から仲が良く、また家も隣という事で、事あるごとによく二人で遊んだ。
しかし小学校の途中で、突然、絵莉菜の両親が勤めていた研究所の不慮の事故で、二人とも重傷を負ったらしく、お父さんの方は奇跡的に
回復したものの、未だ事故の後遺症が残っている為に入院中、そしてお母さんは残念ながらそのまま帰らぬ人となってしまったらしい……。
詳しい事は知らないが、その時の絵莉菜にはあまりにもショックが大きすぎて、一時、精神的に不安定だった状態だったらしく、そのまま
親戚の家に預けられたそうだ。それから月日が流れ、中学校で再び再会し、今に至っている。
今ではあの事故の事を忘れているかのように、どんな時も笑顔を絶やさず、俺にも優しく接してくれる。それ以上に絵莉菜は、度々俺の家に
来ては家事や料理を作ってくれたりとしてくれる。そんな絵莉菜が俺はいつしか仲の良い友達から、気になる異性へと変わっていった。
それなのになかなかその気持ちを絵莉菜に打ち明けられなくて、結局今日まで幼馴染み止まりで足踏みをしている状態なのだ。
神が俺に与えてくれた絵莉菜との学園生活も残りわずか……。よってこの状況を変えるべく立ち上がるんだ、鍵士!
それにはまずベッドから出なくては……。
「さ、寒い! 寒すぎる!! 本当に今日は4月1日なのか? 4月ってのは季節的に春だろ。春ってのは普通、ポカポカと
暖かいもんじゃないのか。やばい、春をなめてたよ、俺……」
家の外の様子を見てみようと、必死に腕を伸ばしてカーテンを開け、窓越しに外を覗いてみると、なるほど、
一応、街路樹として植えてある桜並木は満開、花びらが風に乗ってこちらへと舞いながら飛んでいる。そして多くの学生や会社員がその中を
軽快に進んでいる。みんな春の陽気のせいか、うきうきしているようで、中でも学校の新入生や、新社会人たちは期待に胸を膨らませているようだった。
――ああ、これではベッドから出ることさえままならない……。もう諦めよう、俺の青春バイバイ……――
「ドスッ!」
「ぐはっ!?」
突然の衝撃に何が起こったのか全く分からなかった。自分の心の中で青春に別れを告げていた瞬間の出来事だった。
謎の衝撃の原因は鍵士の視線の先にあった。そこにはまさしく鍵士のシスター、「久遠 未由」の姿があった。
つまり彼女の華麗なミドルキックがこれまた見事に鍵士の脇腹に突き刺さったのである。
その凶悪的な攻撃能力を笑顔の裏に潜ませた、危険な妹。それが未由なのである。ここまで危険な妹はおそらく、
世界中探し回ってもいて数人、つーかこいつしかいないんじゃねえ、と思うほど絶滅危惧種並に貴重だろうな。俺なら即レッドデータブックに載せる。いや本気で……。
いつしか付いた二つ名は『暴虐たる烈火の鬼妹』。まあ勝手に俺が命名したのだが、何にしても恐ろしいことには変わらないんだ……。
未由は腕組みをしながら俺の方へと歩み寄り、俺との距離をさらに縮めた。短めの茶色の髪の毛の一本一本が
まるで燃えているように、揺らいでいた。
「お兄ぃ、新学期早々、遅刻をしようとはたいした心意気だね。さて、あと3秒以内に起き上がらなかったら、果たして
お兄ぃはどうなっちゃうんだろ~ね」
即座に身の危険を感じた。これは単なる脅しなんかじゃない、本気で俺を殺る構えだ。
――これじゃあ起きあがるどころか、一生起きあがれなくなってしまう……!――
季節外れの寒さは、今や背筋の寒さに変化していた。
鍵士はすぐさまベッドから跳び起きた。
「こ、これでいいだろ、未由。ちゃんと3秒以内に起きたし……」
と言い終わる前に、2度目の悲劇が鍵士を襲った。
「バシュッ!」
「お兄ぃの変態! もう二度と起こしに来ないからぁぁあ!!!!」
そう叫ぶと、未由は部屋のドアを荒っぽく開け放ち、1階へとドタドタと降りていった。
今度は回し蹴りが鍵士の脳天を貫通したらしく、額からはぷしゅ~と血が噴き出している。
「未由のぱんつ、今日は白色かー……」
意識を失いつつも、未由の回し蹴りによって丸見えだったぱんつの純白さが頭の中にくっきりと残っていた。
どうやら蹴られた原因は俺の下半身にあったらしい。気を失ってから、少し時間が経ち、ようやく起きあがってみて
気付いたのだが、何のはずみでか、履いていたはずの半ズボンがずり落ちていたのだ。つまり未由の目の前には
俺の輝かしい青色のトランクスがあった事になる。これでは未由に蹴られるのも当然か……。
ゆっくりと立ち上がり、まだズキズキと激痛が残る額と脇腹をさすった。
「案外、あいつなりに手を抜いたのかもなー。未由のやつ、可愛いところもあるじゃないか……」
俺は若干のうれしさを抱きながら、1階へと階段を下りていった。
* * *
リビングのテーブルには既に未由の手作りの朝ご飯が整然と置かれていた。ミルクにサラダ、トースト、それにハムエッグ。
いつものメニューが並んでいた。キッチンでは未由がめまぐるしく手を動かしている。どうやら弁当を作っているようだ。
まださっきの痛みが引いていない脇腹をおさえながら、イスに座り、テレビを付けた。
画面に映ったのは朝のニュースだった。なんとなく見ていると、一つ、目を引く事件があった。
『紅華ヶ丘町、またも惨殺死体。今週に入り、3件目の同様の事件。警察は現在、現場での聞き込み、犯人の捜索と同時に、被害者の身元を確認中だが、死体の損傷が激しく、
確認は難航している状況である。他の事件も同様に、死体は何十ヵ所も刃物のようなもので切り刻まれており、犯人の狂気的犯行が伺え、
近隣の住民は不安の色を隠せない……』
――紅華ヶ丘町って俺たちのとこじゃん! こんな事件が起きていたのか……。しかし、物騒な世の中だな。
用心しないとな――
「お兄ぃ、いつまでテレビなんか見てるの! さっさと朝ご飯食べちゃってよね。じゃないと、本当に遅刻しちゃうよー!」
「分かった分かった、いま食べるから。ところでさ、未由。紅華ヶ丘町で起きた殺人事件、知ってるか?」
トーストにかじりつきながら、さっき見たニュースの事について鍵士は聞いた。
「殺人事件? ああ、それねー。友達から聞いたけど、何だか凄いらしいね。何たって身元が確認できないぐらい、切られてんでしょ?
完全にミンチ状態らしいってね。わたしも犯人に見習って、今度お兄ぃにやって見ようかな~」
飲んでいたミルクが吹き出しそうになった。いくら何でもこの冗談はヤバすぎる。たとえ未由であってもだ。
「アハハ、冗談だってば! 大丈夫、そこまではさすがにやらないよ。それよりお兄ぃ、本当に早く食べてよネ。
もうお姉ぇはとっくに家を出て行ったんだから」
そういえば姉貴の姿が見えない。いつもならこの時間、まだベッドにいるはずなのに……。
「なぁ、未由。なんでそんなに早く姉貴が家出たんだ~? いつもの姉貴なら、起きるのもっと遅いじゃんか」
「お姉ぇをお兄ぃといっしょにしないでよ。お姉ぇは生徒会長の仕事で、始業式の準備があって、それでいつもより
1時間早く、家を出たの」
そうだった。姉貴は生徒会長だったんだ。姉貴の名前は「久遠 遙」。俺より1つ年上の高校3年生。去年の暮れ、
学校側から国立アルカディア学園本校の生徒会長に任命され、今年度より学園全体を取り仕切るトップに君臨するのだ。
確かに姉貴は、俺が言うのも何だが、容姿端麗・品行方正・頭脳明晰という完璧超人の代名詞とも言えるこの三拍子を
備えており、そればかりか、男女問わず全ての生徒に、まるで母親のように優しく接し、そのためか『学園のマリア』とも
例えられる。その凄まじい人気とカリスマ性は全校トップとされている。また、弓道部の主将も務めており、その腕前は
全国屈指の強豪の1人として恐れられているほどだ。
非凡な姉貴と平凡な俺とは、まさに別次元同士であり、兄弟であることが全くの嘘としか言いようがない。だがそれ以上に
俺が感じるのは、姉貴の学園内での姿が、本当は猫をかぶっているとしか言えないからだ。
家にいるときの姉貴は、それこそ俺と同じように、グータラでめんどくさがりや、生徒会長とはまるで縁の無いようにしか
見えない。俺の知ってる限りでは、姉貴が家事をやることは無いに等しい。
前に1度だけ、未由が風邪を引いて寝たきりになり、絵莉菜に助けを呼ぼうとしたのだが、絵莉菜も未由の風邪がうつったらしく、
寝込んでいたという、奇跡的な1日があり、仕方なく姉貴が料理を作ることになったのだ。
当の本人は自信があったらしく、俺も姉貴の手料理に期待して1口食べてみたのだが……。
その日は1日中、目を覚まさなかったらしい。俺自身も気絶していたので、よく覚えていないのだが、それほど姉貴の
料理は危険ということだ。いったいどうすれば致死料理を作ることが出来るんだ、としか言いようがない。
妹共々、久遠姉妹は危険だということだ。
* * *
未由に急かされながら、制服に着替え、玄関のドアを開けると、通学路は驚くほどの数の人たちが、これまた驚くべきことに
全員が皆、猛然と走っている。胸にペガサスを模った校章が描かれた制服を着た、アルカディア学園の生徒たちに、ビシッと
スーツできめた会社員がやれ急げと、彼らの向かうべき場所へと走っている。
もちろん俺たちもゆっくりしてはいられない。他の生徒たちと一緒になって、いち早く学校に向かわなければならない。しかし
とうの未由は、まだ家の中から出てくる気配はない。
「未由ー! 何やってんだよ、早く行こうぜ」
「ちょっと待ってよねー! 今行くから」
すると未由が手に何かを持ちながら大慌てで出てきた。そして出てくるやいなや、手に持っていたものを無理矢理胸へと押し当てられた。
「はい、お兄い。コレ!」
見ると綺麗な黄色の布で丁寧に包まれた物が押しつけられていた。
「何だ、これ?」
「もう、見てわかんない? お弁当、お兄ぃのお弁当! これを作ってたから、遅くなったんだよねー」
「お弁当? 今日は始業式やるだけなんだから、弁当は必要ないだろ。それに昼飯なら、コンビニで買えばいいじゃんか」
「ダーメ! そうすると食費がかさんで、もったいないでしょ。弁当ならその食費が抑えられて、その分をわたしのお小遣いにできるし!」
「ああ、そういうことかー」
――ちょっと待て。それは未由だけが得するんじゃないのか……?――
「なあ、未由。俺だけ損してる気がするんだが?」
未由の拳がすぐさま唸り声をあげる。その速度、0.2秒。かわせるわけがない!
「おい、何ですぐに殴るんだよ! しかも裏拳ってオイ! そりゃ反則だろ」
「何の事? それに裏拳が反則なのはボクシングだけ。空手やプロレスじゃ当たり前にやってるよ」
もういい、ともかく今はそんなことより学校へ行くことを最優先事項として実行しなくては!
俺たちの住む町、紅華ヶ丘町は、元々片田舎のような場所だったのだが、国立アルカディア学園が町の中心部に建設されたことによって、
そこを中心に、様々な施設が造られ、今では日本国内随一の敷地面積を誇る学園都市となったのだ。学園周辺には
ファーストフード店やカフェ、オシャレなブティック、大型スーパーマーケット、そしてアミューズメント施設などの多くの
商業施設がひしめき合うように立ち並び、学生にとってはまさに「ユートピア」なわけである。
しかしそれと同時にこの町が有名なのは、都会的な町と美しい自然との2つが調和されているという点である。町中には
多種多様の街路樹が植えてあり、少し遠くへ足を伸ばせば、山に海、広大な自然公園があるのだ。
ま、俺たちにとっても春に花見、夏には海水浴、秋なら紅葉狩り、そして冬にはスキーと、四季折々の自然の楽しみ方があって
嬉しい限りなわけである。
走り出してから約10分。ようやく学園のシンボル、時計台のてっぺんが見えてきた。
いつ見ても思うのだが、なぜこの学園はここまで大きいんだろうか。この時計台だって、尋常無い高さを誇っている。ゆうに100メートルは
超えているはずだ。それどころか他の学園の建物、施設は桁違いにスケールがでかすぎる。巨大学園都市というのは分かるが、ここまでくると
常識を疑ってしまう。こんな学校、他に日本中、いや世界中探したって恐らく無いだろう。いや絶対無いと確信できる。
校門が近づくと、走る生徒の数は、電車通勤の生徒も合わさり、恐ろしいほどの学生で道路が溢れかえっている。それでもさすがは巨大学園都市なわけで
通学路の幅も計算し尽くされたように長い。だから誰もが皆、無事に登校出来るわけである。
――何だよ、みんな俺たちと同じで遅刻ギリギリじゃん。それにしてもここまで多いとはな――
腕時計を見ると、7時55分18秒……! ってことは本礼の鐘が鳴るまで、残り僅かたった5分か……。いや、これなら間に合う!
最後の希望と共に、一気にラストスパートを鍵士はかける! そのはずだった。
「お兄ちゃん!」
どこかで聞いたフレーズと共に背中に何かが乗った。その直後、未由の甲高い声が辺り一帯に響いた。
「り、凜ちゃん!? 何でココにいるのー!?」
俺たちの近くにいた生徒は、未由の声に驚いたらしく、一斉にこちらへと目を向けた。俺自身も瞬時に後ろを振り向いた。
「えへへ、お兄ちゃんひさしぶりっ! 会いに来ちゃった」
「り、凜!? もしかして凜なのか!?」
金髪碧眼、ツインテール。おまけに俺の肩にも届かない身長。なのに俺と同い年という矛盾性を秘めた、破格の17歳。間違いない。
俺の背中に乗っていたのは、紛れもなく「鈴毬 凜」、その人だった。
「もしかしなくても凜だよぉ~! ぷぅ~」
凜はその小さな頬を膨らませた。
「わりぃ、わりぃ。でもよ、凜。お前、中学卒業した後、中国に留学したんだよな?」
「それなのになんで、こんな場所に、しかもこの学校の制服を着てるの?」
未由は実の兄の背中に乗り、「お兄ちゃん」と呼んでいる凜を複雑な感情で感じながら、言った。
凜はそっけなく答えた。
「なんでって、もちろんお兄ちゃんと同じ学校に通うためだよ? まあ他にもいろんな理由はあるけどね。
とにかく寂しかったんだ、お兄ちゃんに会えなくて」
「ほんとにそんなくだらない理由なのか、凜?」
「な、くだらなくなんかないよ! これは一世一代の行動なんだから!」
未由は鍵士の肩をたたきながら言った。
「なんかメンドくさそうだから先行くね、『お兄ちゃん』。ま、頑張ってねー」
そう言うと未由はそそくさと早歩きで行ってしまった。
「お、おい待ってくれ未由! なんで俺をおいてくんだよー!」
「いいじゃん、お兄ちゃん。一緒にゆっくり学校へ行こうよ。だいたい、ここの学校の生徒はなんでまた、こんなに急いでるの?」
凜のやつ、明らかに今、俺たちがどういう状況にあるか分かってない。ゆっくりなんてほど、俺にそんな猶予はもう残ってない。
凜をおぶりながら走るのは少々厄介だが(ウエイトもあるが、この場合周りの視線の方がツライ……)、仕方あるまい。
今俺に科せられている課題はただ一つ。とにもかくにも本礼までに校門を抜けることだ。
「しょうがない。凜、しっかりつかまってろよ!」
「ラジャー☆」
凜は鍵士が今から何をしようとしているかも知らずに、笑顔で敬礼をした。
鍵士は背中に乗った小さなものの両足をしっかりと握ると、大急ぎで走り出した。もはや周囲の視線なぞ気にも止めず、ただ猛然と
生徒と生徒との間をかいくぐりながら、校門へと向かっていった。
さて凜を背中に乗っけたまま走り出してからまだ1分も経ってないだろう、しかし鍵士の目の前には
幻でもなく、間違いなく、立派な金文字で『国立アルカディア学園』と書かれた校門があった。
――やった、とうとう校門まで辿り着けた! しかしこんなに家から学校まで長かったけな?
まあいいや、本礼もまだ鳴ってないし、とにかくこれで一安心だな――
しかしそれほど世の中は甘くなかった。よくみると校門の前には学園一の鬼教師として名を轟かせる、
生徒生活指導及び学域管理主任、おまけに剣道部顧問、塚原が待ち構えていた。左手には遅刻者の名を記名する、通称
『拷問リスト』。そして右手には今まで幾多の生徒に地獄を見せたと思われる、恐ろしきダークウェポン、竹刀が握られている。
噂ではこの竹刀に付着したシミは、生徒の血の痕だというのが通説なのである。だからこそ決して竹刀と言って侮ってはいけない。
あんなものに対抗する力なんて平凡な俺にはない。俺の手に握られているのは、勇者の武器ではなく、
背中に乗りながらはしゃいでいる凜の両足なのだから。
――でも、何で塚原がいるんだ? まだ時計は8時になってないんだがな?――
その時、本礼を知らせる学園の時計台の上にある巨大な鐘が、これまた大きな音を奏で始めた。
「ま、まさか! 俺の時計、少しずれてるのか!? それじゃあ遅刻なのか……」
校門まで残り5メートルほど。なのに俺の置かれている立場は結局遅刻者なわけだ。あんなに一生懸命走った自分が惨めに思えてくる。
――終わった。俺の記念すべき高校2年生の学園生活はこうして幕を閉じたのだった……。
「お兄ちゃん、マダあきらめちゃダメだよ!」
凜に励まされるとは思わなかった。遅刻したのが自分の責任だとも知らずに。
「あのなぁ、凜! 遅刻したのはお前のせいなんだよ。これで俺とお前は共々、地獄部屋行き決定だ……」
「だからぁ、マダ大丈夫だってば、お兄ちゃん!」
ウインクしながらガッツポーズをとる凜。いったいお前の小さな身体のどこから、そんな自信が生まれてくるんだ?
「じゃあ、なんか秘策でもあるのかよ? この状況下で」
「モチロンだよ! 要はさ、校門を超えればイイんでしょ?」
「ああ、まあ、そうなるかな……」
若干、凜の質問に不安を感じた。こいつの案というぐらいだからよほど非常識なのは見当が付くのだが。
「ウン! それじゃあハナシはカンタン! 校門を跳び越えちゃえばオーケーでしょ☆」
そりゃいい考えだ! んじゃあ、さっそく……。ってオイ! 完全に考えがぶっ飛んでるぞ。そもそも塚原の存在は
最初から無視なのか? いくらなんでも無茶苦茶すぎる。そもそも俺はとにかく、凜に校門を跳び越えるほどのジャンプ力が
あるかどうかということ自体、疑問を抱いてしまう。
「なあ、それ無理じゃないのか? お前、そこまでジャンプ力あったっけか?」
「そんな心配してるの、お兄ちゃん? それなら答えは一つ。安心してまかせてよ。秘密の特訓もしているんだから!」
「『秘密の特訓』って何だよ、その不可解キーワードは!? それ以前に俺に言ってる時点で秘密になってないし……」
「まあまあ、そこら辺はつっこまないでよ。とにかく選択肢は無いわけだし、ここは一つ、任せてよ!」
確かにこのまま捕まるよりかは、コレを確かめてから捕まった方がいいか……。
「よし! わかった、今は凜を信じるからな」
こうなったらヤケクソだ。やるだけやってそれから死になさい、みたいな葛城さんのセリフもあるわけだし、
少しの望みにもかけるほかない。
「ウン、それじゃあお兄ちゃん。さっそく走るよ!」
「わかった。あれ、凜、背中から降りるのか?」
凜は今まで乗っかっていた俺の背中からゆっくりと降りると、走る体勢へと構えた。
「お兄ちゃんに余計なめいわくはかけたくないからね。準備いい、お兄ちゃん!」
「あ、ああ! いつでもいいぞ!」
――いつのまにか凜も結構大人っぽいこと言うようになったじゃんか。見た目はまだまだ子供だけどな――
「じゃあ行くよぉ!」
凜の声を合図に俺と凜は同時に、校門へと全速力で走り出した。
「よし、今だ! 跳ぶぞ、凜!」
「了解ー!」
鍵士と凜の2人が走ってくるのに気付いた塚原は
「な、お前ら! 何する気だ!」
その瞬間、鍵士と凜は空を駆け抜けた。その跳びッぷりは全米が湧いたそうな。極めて短時間の出来事なのに
とても気持ちよかった。塚原は自分の真上にいる俺たち2人に気付いているものの、あまりの突拍子さにただただ
ぽかんとしているだけだった。凜はまるで楽しんでいるかのように、満面の笑顔で、しかも軽快に跳んでいた。その
跳躍は凜の体格に見合わない動きだった。
一瞬だったが、凜の履いていた制服のスカートが風で浮き上がり、そのおかげで水色の縞模様のパンツが俺の視線に
入ってしまった。だが、あまりの堂々さに興奮さえしなかった。いや、出来るはずもない。相手が凜なのだから、当然
なんだが。
「バンッ!」
見事着地に成功。その場で大きな着地音が響き渡った。それと同時に大きな衝撃が俺の身体に素早く行き渡った。
足の裏にも激痛がはしる。それでも、未由の暴力に比べればどうということなどない。
「いや~、楽しかったね、お兄ちゃん! やっぱりこの学校に入学してよかったよ!」
それはよかった。満足してくれて。相変わらず凜は泣くどころか、とても楽しそうにしている。本当にお前は
何なんだ? 男の俺でさえ少し怖かったというのに。
「コラ、お前ら! とっくに8時は過ぎているんだ。それなのによくも私の前で校門を乗り越えたな! とにかく
早くこっちに来い!」
塚原がようやく事態を把握したらしく、俺たちを捕らえようと歩み寄ってきた。
「マズいぞ、凜……! ひとまず今は塚原から逃げるぞ!」
「またまた了解~☆」
俺と凜は一目散に高等部のある校舎へと走った。どうやら今日は休まる時間など俺にはなさそうだ。いや、もしかしたら
今日だけじゃない、今年一年、大変そうだ……。
* * *
歩いている途中、凜は、自分がいなかった間に俺の周りで何かあったとか、中学校の頃のみんなは今どうしているかとか、
様々な質問を俺に投げ掛けてきた。その1つ1つを凜が分かるように教えてやった。
「ふ~ん、だいたい、いなかった時の3年間の様子は分かった。つまりお兄ちゃんに彼女はまだいないってことなんだね!」
「何でそうなるんだよ! まあ確かに彼女がいないのは事実なんだが……」
「よかったー! お兄ちゃんに彼女がいなくてホッとしたよ!」
「だから俺に彼女がいないことになんでそんなに喜ぶんだよ、凜!」
「だってお兄ちゃんが誰かに取られちゃうなんてイヤだもん……」
瞳をウルウルさせる凜の顔は、明らかに真面目に悲しそうな顔だった。
「わかったわかった、わかったから頼むからこんな所で泣くな。心配しなくても俺に彼女なんか当分出来やしないから」
「ホント! じゃあいつまでも一緒だね、お兄ちゃん!」
ついさっきまで涙で濡れていた凜の顔が、パッと今度は明るい笑顔に変わった。その移り変わりのスピードには驚いた。
――いつまでもは無理だと思うが、彼女が当分出来ないのは本当かもしれないしな――
「あ、そうだ。お兄ちゃん、この学校ってサ、どんな学校なの?」
「どうって、普通の学校だが。普通に授業はあるし、放課後には部活も活動しているし、学期末には試験もある。それに学内施設も
一通り充実してる。それにたくさんの生徒がいる。ってな感じかな」
「それじゃあ、今日は始業式だから、明日、学内回ってこよーかな。一応、この学校の事、知っておきたいからネ☆」
「忠告しておくが、それは多分無理だぞ」
「エェ! な、何で?」
「言い忘れたが、この学校、スケールの大きさだけは普通じゃなく、異常だからな。はっきり言って、1日でこの学園全部を
見て回るなんて、不可能なんだよな。ディ●ニーランドどころの問題じゃないのは、確定だな」
「エ~、でもそれじゃあ……」
「安心しろ、俺も明日一緒に回ってやっから。重要な場所を厳選して見せてやるから」
「ホント! やったぁ!」
「ただし条件がある。凜、絶対にこの学園内では、いつもみたいに『お兄ちゃん』なんて言葉で呼ぶなよな」
「どうして? なんで『お兄ちゃん』て呼んじゃいけないの、お兄ちゃん?」
凜は本気でこの理由が分かっていないようだった。
「どうしてって、決まってるだろ! 普通の人なら、同じ学年の生徒同士で『お兄ちゃん』て呼ぶのは変に思われるだろ!
もし言ったら本気で困ることになっちまうからな。特に俺が」
不思議がっていた凜もようやく事の重大さを把握したらしく、素直にうなずいた。
「了解でーす☆ なるべく言わないよう気をつけるよ、お兄ちゃん!」
言ってるそばから……。本当に分かっているのか、凜のやつ……。はっきり言って不安すぎる。確かに、中学校の頃から凜には
『お兄ちゃん』と呼ばれているし、完全に俺としてもその呼び方には慣れている。逆にそれ以外で、例えば『久遠くん』みたいな
感じで呼ばれたらどうだろうか、全く持って違和感しか残らない。だとしても、ここは高校。あの頃みたいにするわけには
いかないのも事実だ。果たして凜はちゃんと約束を守ってくれるのだろうか……。
「ところで凜、そういえばさっきは聞けなかったけどよ、なんで中国に留学したんだ? 親の都合ってのは聞いたけど」
「ああ、ソレね」
凜は頷いたが、少し考えている様子だった。
「ヒ・ミ・ツだよ☆」
凜が人差し指を立てながら横に振った。
「なんだよ、それ。そんなに秘密にするほどのことなのか?」
「う~ん、まあね。でも理由ならもう少し経ったらきっとわかるよ」
この時はまだ凜の言ったこの言葉がどれだけ深い意味を持つのか想像もしていなかった。そう、この時から既に俺の学園生活が
大変な方向へと向かっていたのだった……。
PR