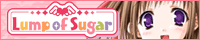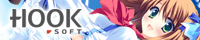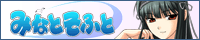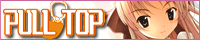凜と一緒に歩くこと5分。ようやく高等部の校舎が見えてきた。
「おっきいねー! これが高等部の校舎なの?」
「ああ、このバカでかい建物が、俺たち高等部の校舎。広いから俺から離れるなよな。そうじゃないと迷子になっちまう……」
言い終わる前に、俺の横にさっきまでいた凜の姿は無かった。
――っとに、凜のやつ、ほんとに人の話を聞かねえな……。探してやれるほど、時間に余裕があるわけじゃないってのにな――
凜を探すか、ほっとくかで悩んでいたその時、不意に誰かに肩を叩かれた。
「ようやくおでましかい、我が親友、久遠よ!」
この独特な声質と口調、後ろを振り向くと、腐れ縁の悪友、一之瀬敦志がそこにいた。
「ようやくで悪かったな、敦志。朝からいろいろと事件に巻き込まれてな……。実のところ、今もある女子を捜そうとしていた
ところなんだよな、これが」
すると敦志の口から意外な答えが返ってきた。
「お前が捜している女子? ああ、彼女のことか!」
「お前、知ってるのか! そいつがどこにいるのか」
「もちろんだとも、久遠。そのことなら心配はいらん。彼女ならもうとっくに教室、それも、俺たち2人と同じA組の教室だ!」
――今年も敦志と同じクラスだってことをつっこむのはおいとくとして、そうか、凜のやつ、俺が見てない間に自分の教室に
行ったのか。あれ、でも待てよ? よく考えたら敦志のやつ、中学時代から凜のことを知ってるのは当然だとしても、なんで俺が
凜を捜していることを知ってるんだ?――
「おい、彼女に会いたいんだろ! 早くこっちに来い、久遠」
「お、おお。今行く」
俺の疑念が募っていくのとは反対に、敦志は悠然と俺を連れ立って、生徒で溢れかえった廊下をかいくぐりながら、どんどん
目的地のA組の教室へと向かっている。
「あのさ、敦志。ちょっと聞きたいことがあるんだが」
「久遠、心配しなくとも、お前と心の繋がった親友であるこの俺には、以心伝心で、お前の聞きたいことぐらい分かっている!
そもそも、お前が捜す女子など、彼女1人しかいないだろうしな」
――やっぱり、敦志のやつ勘違いしてやがる! おそらくこいつの言う『彼女』とは……――
ちょうどその時、俺と敦志はA組の教室に到達していた。
「存じていると思うが、既にクラス替えの発表は終わっている」
「ああ、知ってる。それよりさ……」
「俺はな、久遠。今日、つまり高校2年の新学期初日に、お前が必ず遅刻をするだろうと確信していた。まあ、いわゆる暗黙の了解と
いうものだ。そこで親切にも、お前が恥をかかぬようにお前のクラス番号も確認しておいたのだ」
敦志は誇らしげに言った。俺にとってはどうでもいい問題というか、恥ならしょっちゅうかいてるから別段、そこまで心配して
いなかったんだがな。
「そりゃどうも。で、その俺が捜している女子ってのは……」
「どうやら今年も去年と引き続き、お前と一緒に学校生活を送ることになったようだ。さすがに8年連続同じクラスってのは俺も
驚いている。まさに久遠と俺は腐れ縁だな」
そうは言ってる敦志だが、あいつはあいつで多分、俺と同じクラスになって本心は喜んでると思うし、かく言う俺もなんだかんだ
いって結構嬉しい。人付き合いがあまり得意じゃない俺にとって、敦志は男友達の中で、唯一、気兼ねすることのない親友だと
いっても過言じゃない。しかし、せっかくさっきの会話でこの話が出てこないよう、ツッコまなかったていうのに、本当に敦志は
期待を裏切らないやつだよ、まったく。
「さて、本題に入ろうか、久遠。ここ、A組の教室にお前がお捜しの『彼女』がいらっしゃるぞ!」
敦志はA組の教室を指差しながら、大声で叫んだ。俺らの近くで話していた女子2人組が、ビクッとなってその場から離れた。
「あのさ、敦志。やっぱお前勘違いしてないか? 俺が捜してるっていう女子は鈴毬り……」
凜の名前を出す間もなく、敦志は教室のドアを勢いよく開け放った。
ここで紹介しておくが、一之瀬敦史の短所の1つ、それが『勘違い』というものである。敦志の行動は時にあいつの勝手な勘違いに
よって引き起こされることがある。この状態になると、ただひたすら自分の勘違いによって突っ走ってしまうので、誰にも止められ
なくなってしまう。一応、この状態の敦志を停止させられる人間がこの学園に1人存在するんだが、現状では、当然のことながら
その1人はいない。
「さあ久遠、お前の捜す愛しの彼女、如月はあそこに……」
やはり勘違いしていたか。敦志の言っていた『彼女』というのは、俺が捜していた凜のことではなく、俺の片思いの相手、絵莉菜の
ことだったようだ。大体の予想はついていた。そもそも俺自身が敦志の立場だとしたならば、同じ考えをしたかもしれない。俺の頭は
敦志のそれと徐々に近づきつつあるからなおさらだ。
しかしそんなことを考える必要もなく、俺の目の前には悶絶した敦志の亡骸がそこにあった。
敦志に急所突きを喰らわせたのは、さっきも言った、学園でただ1人の敦志キラー。瑞樹瑠璃、その人である。俺はただただ、この
惨状に怯えるしかなかった。どう見てもやり過ぎとしか言いようがない。
――未由といい、瑞樹といい、どうして俺の周りにいる女ってみんなこんなに危険なんだ!? これじゃあ俺の人生、本気で命懸けじゃ
ねえか……!――
「ホント、このバカは懲りないわねー! せっかくクラス替えして、みんな新鮮な気分でいるってゆうのに。第一、このバカと2年連続で
同じクラスだなんて、新学期早々最悪だわ。ってあれ? 鍵士じゃん! いつからそこにいたの?」
「瑞樹が敦志に急所突きを喰らわせた時から」
「そうだったんだ。ゴメンね、ついこのバカに気がいっちゃってねー。あれ、てことは鍵士もアタシと同じでA組?」
「ああ、そういうことになるな。今年もヨロシク頼むよ」
「まあ、このバカと同じクラスだってことが判明した時から、薄々感づいてたけどね。それよりサ、やったじゃん鍵士!」
「え、何がやったんだ、瑞樹?」
「鈍いわねー。絵莉菜も私たちと同じA組だよ~! 鍵士にこのバカと、そしてアタシに絵莉菜。私たち4人組がまた同じクラスにいる
なんてなんかスゴイよね。 それでさ、今年こそ絵莉菜にコクるんでしょ? 頑張ってね!」
「うっせーよ、瑞樹。お前こそ、敦志にもっと素直になった方がいいんじゃないか?」
「このバカと同じクラスになったことには、アタシの本心的にはウレシイよ、実際」
――何だって!? てっきり冗談で言ったのに、本気かよ、瑞樹!?――
「だってホラ、このバカ痛めつけるの、意外とストレス解消になるから。どうも学校てストレス溜まるんだよねー。それに結構このバカで
遊ぶの楽しいしね」
「ハハハ、そうかもな」
苦笑いするしかなかった。瑞樹瑠璃、やっぱりこいつは人間の皮をかぶった子悪魔に違いない。絶対に恋愛感情みたいなものを瑞樹に
抱かないほうが身のためだ。
「ところでさ、絵莉菜の姿がどこにも見当たらないんだが?」
「そういえばそうね。ま、あんなに親切な絵莉菜のことだから、先生の手伝いでもしてるんじゃないの? ほんと絵莉菜とはいつも一緒に
いるけど、あそこまでどうして人に親切になれるのか、未だに理解できないのよねー」
そりゃそうだ。絵莉菜と瑞樹の二人は仲のいい二人組なのは周知の事実だが、二人の性格はまるっきり正反対だ。絵莉菜はとても優しく、
誰にでも親切にする。逆に瑞樹はと言うと、外面なら、ショートカットでボーイッシュスタイルをしていて、まるで顔立ちの良い男子のように
見える。それが男子にとってはかなりイイらしく、人気も高い。しかしその顔とは裏腹に、瑞樹はS気質を持ち、男子生徒達を手玉に
とっては楽しんでいる。そのため、一度瑞樹の毒牙にかかった男は、当分女性恐怖症になってしまうと、被害者から聞いたこともある。
そんな二人の共通点は、おそらく両方とも男子にモテることだろうか。
絵莉菜はもちろん、瑞樹も外面だけ見れば可愛いと感じる。そんな二人とよく喋っている俺は、よく男子から羨ましいと言われているが、
なるほど、確かに俺は恵まれてるのかもしれないな。
だがやはり一番気になるのは、瑞樹と敦志の関係だ。
敦志曰く、自分は自他共に認める女好きだが、瑞樹には全くの恋愛感情など抱いておらん。むしろ、女としての魅力をあいつからは感じない
と言っている。
最初、俺は無類の女好きの敦志に限って、美人な瑞樹を放っておくとは到底思えなかった。しかし、敦志は本当に瑞樹に対して、今日の今まで
なにも起こしてはいない。当の瑞樹本人も、敦志については、学校の噂で聞いたことがあり。敦志も新たな被害者にしようと考えてたものの、
実際、ナンパどころか完全に無関心のような反応をされ、いつか敦志を見返してやろうとよくわからない闘志を燃やしている。
そんな背景から、敦志と瑞樹は常日頃対立しあい、様々な口論をしている。結局は瑞樹の武力制裁で事は終わるが、二人の喧嘩は永遠に
終わらないだろう。そんなためか、最近周囲からは、案外お似合いの二人として、実はデキてるんじゃないかとよく噂されている。俺もそう
思わなくもないため、試しに一度、二人にその事を聞いてみた。
「そんなわけないだろ、俺と瑞樹に限って。だいたい、いつも言うように、あいつのことを俺は女として見てないんだよ」
「あのバカと恋人? 頭大丈夫、鍵士? あのバカと付き合うぐらいなら、鍵士と付き合った方がまだマシ。あ、いっとくけど、もしもの話だから」
否定、否定の嵐だった。まあ、俺には関係のない話なんだが。
* * *
PR