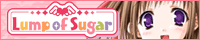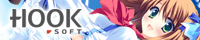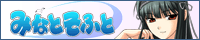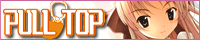そう言えばなんでバンドをやめてしまったんだろう。明確な理由は全く覚えてないが、恐らくめんどくさくなってやめちまったんだろうな。
「さあな。結局、俺には部活とか向いてないんだよ」
「だめだよ、お兄ちゃん! ちゃんと部活には入んなきゃ!」
こんなところで、凜に説教されるとは思ってもみなかった。でも、凜の言うことは確かにもっともな話だ。
「分かった分かった。今日、一緒に学園内を見て回るとき、考えておくよ。さて、朝食も食べ終わったことだし、そろそろ学校に行くかな」
「あー、凜も一緒に行くー!」
凜がドタバタと学校の支度をしに、二階へ駆け上がった。すると、未由も再び台所に戻ると、例の黄色の布で丁寧に包まれてたお弁当を持ってきた。
「お兄ぃ、はい、お弁当」
「やっぱり例のお弁当があるのか。昨日はちゃんと食べたんだし、今日ぐらい購買部でよくないか? 今日は授業も始まるんだし」
「だからこそなの。とにかく、折角作ったんだし、残さず食べといてね」
そのまま、未由もリビングを出て、自分の部屋へと行ってしまった。俺の手には未由の弁当がしっかりと乗っかっている。
「まあ、未由の弁当だけあって美味しいのは事実なんだが、何て言うか恥ずかしいんだよな……」
三人が家を出た時間は、昨日の朝とは違って、いつもより早い時間だった。そのおかげで、学校までの通学路はそこまで人がいなくて、スムーズに歩くことが出来る。それに桜の木々が緩やかな風にのってゆらゆらと揺れる姿がとても綺麗で、気分が晴れるようだった。
――朝早く起きて登校するってのも、随分気持ちがいいもんだな――
しかし相変わらず凜は背中に乗っているし、それを未由がどう思っているか、不機嫌そうな顔をしている。はたから見れば俺たち三人はかなり複雑な関係だろう。俺と本当の妹、そして俺をお兄ちゃんと呼ぶ妹的存在の同級生。絶対におかしい三人組だ。
「なあ未由。どうして不機嫌そうな顔してんだ?」
「何でもいいでしょ、別に。それに不機嫌じゃないから。決して」
いや口調からして完全に不機嫌じゃないか! でもまさか未由が凜に嫉妬とかをするようなタイプじゃないし、俺の事なんか兄とすら感じていない奴だ。その未由が何故そこまで不機嫌そうにしてるんだ?
「あれ? お兄ちゃん、前方に絵莉菜ちゃんらしき人影を発見ー!」
「絵莉菜が!?」
凜の言うとおり、距離にして10メートルぐらい前方には確かに絵莉菜の姿がはっきりと見えた。いや、絵莉菜なら100メートル離れていても俺なら分かる。あの長くサラッとした綺麗な髪、そして頭の両端に付いた黄色いリボン。見間違うはずもない。
「おーい、絵莉菜ー!」
「絵莉菜ちゃーん!」
「絵莉菜さーん!」
三人の叫び声が辺りに響き渡る。近くにいた何人かの生徒はこちらの方を向いたが、もはやそれぐらいは予想の範囲内であり、たいして気にも留めなかった。
「あれ? 鍵士君! それに凜ちゃんに未由ちゃんも! 三人ともおはようございます!」
ようやく俺たち三人に気付いた絵莉菜は小走りでこちらへと向かってきた。その走る姿すら可愛く思える俺は、大丈夫なのだろうか。
「よっす。おはよう、絵莉菜」
「うん、おはよう鍵士君! 今日はみんないつもより早いね。昨日の夜はあんなに騒いだのに」
「そうなんです。お兄ぃにしては珍しいですよね。いつも遅刻遅刻と騒いでるお兄ぃとはまるで別人のようです」
そう思われても無理もないか。だけど昨日の深夜の出来事のせいであまり眠れなかったと言っても、誰も信じてくれないだろう。この事を知っているのは、俺と凜の二人だけのはずだし。
「まあ、俺もたまには早く起きるって事だよ。それで絵莉菜もどうしてこんなに朝早くから学校に行ってたんだ?」
「桜の花がゆっくり見たかったんだ。昨日は人がいっぱいいたからあまり見られなかったんだけど、今日なら朝早く行けばゆっくり見られると思ったの。ほら、とっても綺麗でしょ」
絵莉菜はにっこりと微笑んだ。まるで綺麗に咲く花のように。
――やっぱりこういう学園生活が俺は好きだ。あんな命を懸けた物騒な生活なんて俺には合ってない……――
「ほんとだな。この町の桜って綺麗だよな。確か、この町の名前、紅華ヶ丘って『紅華』って名前の桜の品種から来てるんだってな。だからこんなにも桜が植えられてあるんだよな」
「毎年、こんなにも綺麗な桜を見られる私たち、幸せだよね。ずっとこんな幸せが続いてくれればいいよね」
「ああ」
でも、どうやらそう言うわけにはいかないのが現実なんだろう。俺は幸せな生活をあとどれだけ続けられるんだろうか。 それとも、俺にとっての幸せはそもそも存在していないんだろうか。どちらにしてもこの幸せな日々が少しずつ両手からこぼれおちる砂のように失いつつある感じを受けた。
「お二人さん。そういう話はよそでやってもらえませんかね~?」
不意に肩をポンと叩かれた。
「え!? 瑞樹!? いつからいたんだ、お前!?」
「へっへーん」
瑞樹は右手を腰に当てながらVサインをした。どういう意味なのかは分からんが。
「そういう言い方はひどいなー。まあ、仕方ないか。せっかくの二人の会話を邪魔しちゃって悪かったね」
「そんなんじゃないよ、瑠璃ちゃんー! 私たちはただ、桜の話をしてただけで……」
「いえ。明らかにお兄ぃと絵莉菜さんは仲の睦まじい二人組の会話をしてましたよ。ねえ、凜ちゃん?」
「ウン。二人ともすごく夢中で話してたよ! なんだか凜たち、忘れられてたもん」
なんでよりによって二人とも瑞樹とグルなんだ!? 未由は絶対面白半分で言ってるし、凜の場合は素直に自分の意見を言っているようだ。しかし自分自身もよく考えてみれば、確かに二人の事を完全に忘れていたのかも。あまりにも絵莉菜と話すことで精一杯だったし。
「まあ二人とも頑張ってチョーダイ。その調子ならあと一年以内で結構なところまでいけるから」
――結構なところってどこだよ!? つーか一年以内ってかなりアバウトな発言だな、おい――
「おーい、瑠璃くーん。話はまだかーい?」
すると遠くの方で瑞樹の名前を呼ぶ、自転車に跨った、長身のスラッとした、それでいて足腰にはしっかりとした筋肉のついた、眼鏡をかけたどこぞの韓流スターに似た顔の、つまりイケメンと呼ばれる部類に入るであろう男子生徒がいた。
「すいませーん! 今行きます、せんぱーい!」
「あのイケメン誰? もしかしてお前の彼氏とか?」
「うーん、まあね。というか陸上部のキャプテンの結城先輩。昨日、陸上部のミーティングの時、朝通学する時、自転車に乗せてもらえる事になったってわけ。まあ、確かに結構顔はイケてるし、ちょっとキザな所はウザイけど、通学が楽になるし、いいかな~と思ってね。そう言うわけで、じゃあね~!」
瑞樹はそう言うと、結城先輩と呼ばれる男子生徒の自転車の後部に跨り、背中に抱きつくと、そのまま二人は颯爽と走っていってしまった。
「さすがは瑠璃ちゃん……。あんな格好いい人が彼氏だなんてね」
「お兄ぃも瑞樹さんを見習うべきでは? あんなスゴイ人が近くにいるなんて良かったじゃない」
「あーあ、分かってねえな、未由。瑞樹はああ言ってるけど、本心ではあの結城先輩とかいう人をただの走り屋としか見てねえよ、絶対。これでまた一人、新たな犠牲者が出ちまったな……」
PR