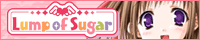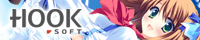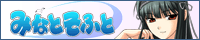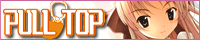鍵士と凜は全速力で夜の街を駆け抜け、ようやく鍵士の家に辿り着いた。
「はあ、はあ。ここまで来れば安心か……。でもあれは一体何だったんだ、凜?」
「『概念の主』だよ。あいつ」
やはりさっきにも男の口から聞いた『概念の主』という言葉。
「だからさ、その『概念の主』って何なんだよ!?」
「やっぱり知らないよね……。それじゃあ今から学校に行くよ!」
「何で今から学校に行くんだよ? もうこんな時間だっていうのに」
さっきの出来事で全く時間のことなど考えてはいなかったが、見てみれば時計は二時を指している。こんな真夜中に学校が開いてるはずなど無い。
「思っていたよりもやつらの行動が早かったからね。凜たちも迅速に行動を起こさないとね。早く学校に行くよ!」
「もう、この際どうでもいいか。今は凜の言うことに従っていた方がいいだろうし」
そう言って凜に言われるがまま、俺は夜の学校へと向かっていった。
「やっと着いた! さあ、学園長先生に会いに行くよ」
夜の学校は昼とは全く違う様子で俺たちを待ち構えていた。それにしても何故学園長先生に会いに行くのだろうか? 確かにこんな夜遅くだというのに校長室の部屋だけはまだ明かりが点いていた。
「学園長先生に? どうしてだよ?」
「それは後で分かるから」
二人は夜の学校に入ると、階段を上り、最上階の学園長室へと向かった。この学園に入学してから、俺は一度もこの学園長室には入ったことがなかった。というより学園長の顔自体、見たことがない。学園長先生の存在は知っているが、何しろ普段生徒達に顔を見せる事などない。生徒会長の姉貴すら、二、三回しか見たことが無いと言うぐらいだ。
「コンコン」
「失礼しまーす、学園長先生」
「ああ、凜君か。入りたまえ」
学園長室は想像以上に広く、部屋の本棚にはびっしりと分厚い本が並んでおり、他にも不思議な物の数々が置かれていた。とにかく学園長先生の部屋だけあってその装飾は豪華絢爛で、その部屋の奥にある大きな椅子に学園長先生らしき人は座っていた。
学園長先生らしき人といったが、その理由は、その人が顔を完全に巨大な仮面らしきもので覆っており、その顔を見ることが出来なかったからだ。服装は真っ白のコートを羽織っており、身体の後ろには十字架のような金属が付けられている。その十字架が何なのかさえ全く分からなかった。
「あなたが学園長先生……?」
「ああ、その通りだ、鍵士君。初めて会ったのは確か十五年前だったかな」
その言葉は若干ノイズが混じったような、変わった声だった。それにどうして俺の名前を知っているんだ? それに十五年前に会ったってのは……。
「学園長先生、『概念の主』が動き出し始めました」
「ああ、鈴毬君。すまなかったね。このような事をさせてしまって。何より鍵士君には危険な目に遭わせたのには悪かったと思う。しかし、私が動けばあちらも本格的に動き出してしまうからね」
そう言うと学園長先生は席を立ち、鍵士の方へと歩み寄ってきた。
「さて、もうこうなってしまっては君にも言わざるを得ないようだ。君が今、どのような状況に立たされいるかをね」
窓から月光が差し込み、学園長先生の顔を覆う巨大な仮面を妖しく照らしている。これから一体、どのような話をされるのか、想像も付かなかった。もはや俺の頭は、様々な疑問でいっぱいだった。
「率直に言おう。君は今、ある者達に殺されようとしているのだ」
「殺される!?」
どうして俺が誰とも知らないやつらに殺されなきゃいけないんだ! 一体何の理由で!?
「驚くのも無理もない。私にも理由が分からんのだよ。それも、どうして君が『選ばれし者』かということもな」
「だから、その『選ばれし者』とか『概念の主』とか、全く分からないんだよ!」
意味の分からない言葉ばかりで、理解したくても分からない。そのことが、俺を苛立たせたのか、溜まっていた疑問と怒り、そして不安感が一気に爆発した。
「お、お兄ちゃん……」
「そんなに怒らないでもいいんじゃないのか、久遠鍵士」
突然、学園長室のドアが開いたと思うと、そこには間違いなく担任の雪乃先生だった。
「ゆ、雪乃先生? 何で雪乃先生までここに?」
「彼女は私の大切な部下でね、こっちの世界を知る人なのだよ」
雪乃先生はすらりとした白のスーツを着ており、手にはたくさんの資料らしきプリントの詰まったファイルを抱えていた。
「久遠鍵士。これから話すことは、お前が今まで生きてきた世界の常識とは全く違う世界の話だ。いいか、全ての常識を今、頭から排除してよく聞くんだ」
常識を排除って、一体……。でも、確かに俺はもう後戻りできない非常識な世界に入り込んでいるのは間違いないんだろうな。
「分かりました。話してください。もう分かってるんです、俺は既に非常識な世界に入り込んでるくらい」
「よし。その潔さがあれば安心だな。学園長、お教えすべき事は全て彼にお話ししてもよろしいのですね?」
「ああ、よろしく頼んだよ、雪乃君」
雪乃先生はコクンと頷くと、手に持っているファイルを開き、話し始めた。
「それじゃあ、久遠鍵士。まずはお前の生い立ちから話すことにしようか。まず、一つ聞くが、お前のお父様、つまり久遠王士さんがどのような人だったか知っているか?」
「親父の事ですか。いえ……、実はよく知らないんです。俺がまだ小さい頃に、病気で亡くなったって、母親には聞いたんだけど……。やっぱり親父がいたって事には今でも実感が持てなくて」
「なるほど。やはりそう聞いているのか……」
学園長先生は寂しげな風に呟いた。
「確かにその通りだ。あくまでも表社会での話だがな……」
雪乃先生はファイルをパラパラと捲ると、一枚のページを見つめながら言った。
「だが、それは事実ではない、作り話であることは知っていた?」
「作り話!? そんな馬鹿な!?」
俺は耳を疑った。この十六年間、親父は俺が小さい頃、病気で亡くなったと、そう母親に言われたことを信じていた。なのにその事さえ嘘だったなんて……。それじゃあ親父はなんで……?
「お前のお父様、久遠王士さんは、人間界において、最強の勇者。それも、あの『世界の六覇者』の一人だったの。それほどあの人は、強かったのよ」
「親父が!? 親父が最強の勇者だって!? 一体どこぞのファンタジーRPG何だよ」
「まあそう思うのも無理もないか。しかし事実、お前のお父様は最強の勇者だったんだよ。人間界においてね。そして学園長先生もまた、その王士さんのかつての友であり、『世界の六覇者』に数えられるほど強い魔法使いなのよ」
もはや本当に話がそちら側の世界に入ってきてるよ……。それも『魔法使い』って……。
「ああ、あの頃が懐かしい。彼は恐らく、現在に至るまで最強の人間であっただろう。あの事件が起きるまではな……」
「あの事件って……?」
「あの事件についての話はまだ彼に教えるのは早すぎるのでは……。それにショックも大きすぎるかと」
「いや、もう潮時であろう。時は満ちた。話すべき事は話した方が、彼のためにもなるからな……」
「一体、何のことなんですか? 勿体ぶらずに話してくれよ!」
学園長先生と雪乃先生、それに凜も知っているのだろうか。三人とも、少し顔をうつむかせていた。
「そこまで言うのならば話すが、恐らく相当のショックを受けるだろうから、それ相応の覚悟は出来ているだろうな」
「ええ。もう、僕には前に進むしかないんですから。後戻りなんて出来ません」
すると、雪乃先生はその重たい口をゆっくりと開いた。
PR